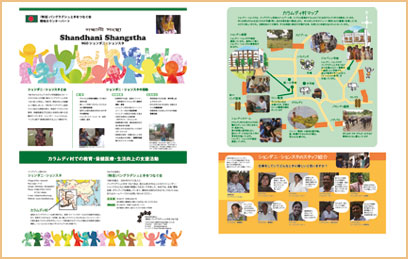ホーム → 会概要
会概要
- 団体名
- (特活)バングラデシュと手をつなぐ会
- 住所
- 〒814-0132 福岡市城南区干隈1丁目16-25 ウェンディハイツ303 地図はこちら
- 代表者名
- 二ノ坂 保喜(ニノサカ ヤスヨシ)
- 電話
- 092-407-7701
- Fax
- 092-407-7702
- E-mailアドレス
- info@tewotunagukai.com
- 設立年月日
- 1989年11月(2004年 NPO法人化) 沿革はこちら
- 会員数
- 150名
- 受賞暦
- 平成19年度、第1回 福岡市 市民国際貢献賞
平成20年度、第10回 西日本国際財団 アジア貢献賞 平成21年度 公益財団法人 社会貢献支援財団 社会貢献の功績
平成31年度 第47回医療功労賞 - 助成金受領歴
- 一覧はこちら
- 会運営
- 総会年1回、理事会月1回 定款(PDF)はこちら
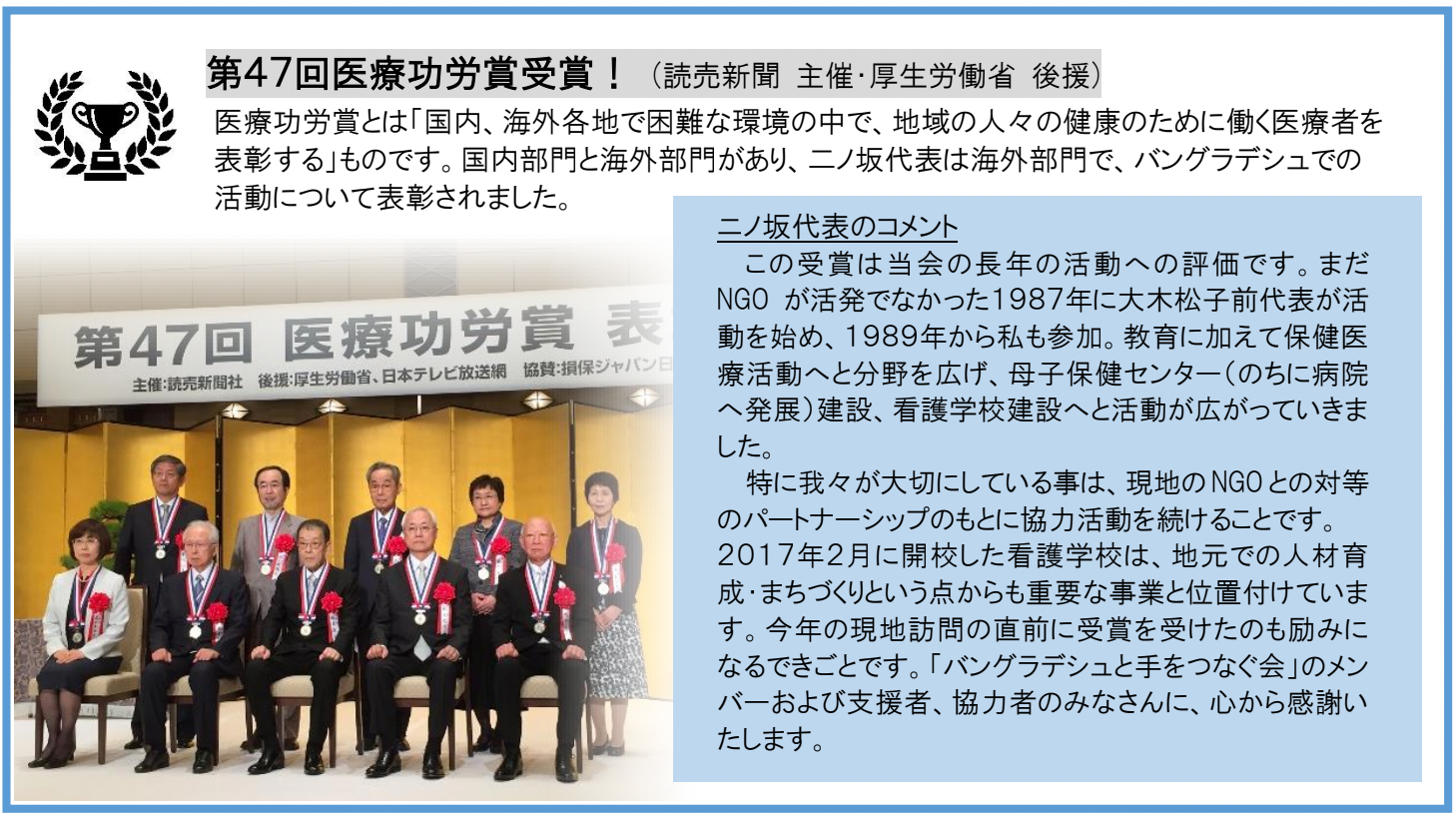
会の理念
- 同じアジアに生きる地球市民として、平等の立場で学びあう。
- 人のいのちを大切にし、子どもたちの成長を助けるため、教育と医療を中心に活動する。
- 村人の自立を助け、必要に応じて援助する。
- バングラデシュでも日本でも、楽しいつどいと交流をまわりへ広げていく。
会ご案内パンフレット(下の写真をクリックするとPDFファイルが開きます)
ションダニションスタご案内パンフレット(下の写真をクリックするとPDFファイルが開きます)
代表メッセージ
二ノ坂 保喜

バングラデシュと手をつなぐ会は、
97年の「バングラデシュに小学校をつくる会」に始まり、
99年「ジャパニ小学校」の完成とともに「手をつなぐ会」として発展しました。
(発足の経緯は、大木名誉代表のメッセージを参照ください。)
そこで、<教育><保健医療>および<生活向上>を柱に、現地のNGO「ションダニ・ションスタ」と連携して活動を行っています。私たちの立場は、ドナー(資金提供者)としてではなく、現地と対等のパートナー(協力者)であると考えています。
続きはこちら
<教育>とは、自分を知り、社会を知り、世界を知ることです。<保健医療>は、人々の生存を確保し、いのちを守り、健康な社会を作る基礎となるものです。<教育>と<保健医療>は、社会の存在と意味を支える基本構造だといえます。この基本構造に十分な資金を投下できないバングラデシュでこそ、むしろその意味が鮮明に見えてくるのです。しかしこれらは、経済的には生産性の高いものではありません。むしろ多くの資源や人材を必要とします。経済的に恵まれない途上国では、生産性の低い部分が切り捨てられ、ますます社会の発展が遅れるという悪循環をくり返します。
バングラデシュは、アジア、世界でも最貧国の一つに挙げられます。偶然のきっかけでバングラデシュと出会い、20年あまりこの国と関わってきました。教育と医療という、個人、社会の存在を支える基礎構造への支援協力活動は、同じ地球上に住む人間として、当然のこととして関わっていくべき事業ではないか、と考えるようになりました。 また、この間の手をつなぐ会はじめNGO活動との関わりの中で、日本人と日本社会のあり方の問題点も見えてくるようになりました。本当の豊かさとは何なのか、共に生きるとはどういうことか、アジアにおける日本のあり方、などさまざまな課題を共に考えながら、歩んでいきたいものです。成人を迎えた「バングラデシュと手をつなぐ会」を今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
2010年3月30日
バングラデシュと手をつなぐ会
代表 二ノ坂 保喜
共同創設者メッセージ ~はじめの「手つなぎ」~
大木 松子

「バングラデシュと手をつなぐ会」の始まりは、1986年夏、
その頃九州大学の留学生だったモクレス・ラフマンさんとわたし
(大木 松子)の出会いでした。
わたしは戦争が終わったときからずっと世界の平和のため、アジアの貧しい人々のために働きたいと思いつづけていました。
だからラフマンさんから、彼の出身地であるカラムディ村に
小学校をつくりたいので助けてほしい、とたのまれたときすぐ引き受けたのです。
続きはこちら
バングラデシュはアジアでもっとも貧しい国といわれています。村の小学校は、木と竹とカヤで村人が自分たちで作りますが、毎年の洪水とサイクロンで壊され流されてしまうのです。
「レンガで造りたいので手伝ってほしい」
といわれて、「バングラデシュに小学校をつくる会」が発足しました。
それから皆さんに募金を呼びかけ、1989年「ジャパニ小学校」が完成しました。

学校を建てるだけでなく、貧しくて学校に行けない子どもたちのために奨学金制度を作ったり、職業訓練を行ったりして、継続的にカラムディ村の人々や子どもたちと、協力を続けていくために、「バングラデシュと手をつなぐ会」を結成しました。
村の人たちも子どもたちも、美しい自然の中で助け合って生きています。その姿は今の社会ではうすれてしまった戦前の日本を思い出させます。
村の人たちは小さい子どもたちが病気で死んでいくことに心を痛めていたので、村に「母子保健センター」を作りたいと強く希望しました。
村人たちの強い要望を受け止めて、建設に取り組み、「母子保健センター」が1995年に完成。その後も村の委員会「ションダニ・ションスタ」と連絡を取りながら教育と医療の分野で協力・援助を続けています。

私たちは、「かわいそうだから助けてあげる」という気持ちではなく、同じアジア人として学びあい助け合いながら手をつないで生きていこうと思います。
この趣旨に賛同される方は、ご連絡ください。
ごいっしょに手をつないで歩いていきましょう。
(名誉代表 大木 松子)
ラフマン・モクレスール

私はバングラデシュのメヘルプール県カラムディ村の出身です。
この村はインドの国境からわずか5キロしか離れていない地域にあり、経済や教育やインフラの面で非常に遅れています。
高校在学中に経済発展のカギとなるのは教育であると強く信じ、地元の若者の協力を得て茅葺の小学校を建設しました。しかし洪水や運営費の不足で、その学校は残念ながら閉校になってしまいました。
続きはこちら
それから皆さんに募金を呼びかけ、1989年「ジャパニ小学校」が完成しました。
1984年に来日し、日本のみなさんの協力を得て、89年に夢に見た小学校を建設することができました。その後、有志でバングラデシュと手つなぐ会が発足され、教育や医療の面で協力を続けています。
今、社会の自立を強く目指しています。そのためにどうすればよいか、時々自己葛藤を感じることがあります。社会自立を目指すならば、私たちの活動は誰に対して行うべきか、答えが出ない問いもあります。社会の発展は誰によって可能なのかも真剣に議論する必要があります。
このような葛藤を手をつなぐ会の会員や現地住民と一緒に議論し、より良い活動に発展させていきたいと思っています。
(共同創設者 ラフマン・モクレスール)